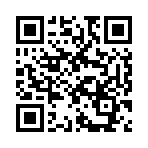スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2012年10月27日
左官鏝
左が鶴首鏝、右が通シメンド
面戸、雀口等に使われる鏝
首が曲がりくねって、鶴の首のような形をしているのでこの名がついた。

面戸、雀口等に使われる鏝
首が曲がりくねって、鶴の首のような形をしているのでこの名がついた。
Posted by 千鳥格子 at
16:32
│Comments(0)
2012年10月26日
民家は生きてきた
町家の魅了の一つに挙げられれるものの中に光と影が織りなす空間美がある。
高窓や天窓によって採り入れられた陽光が長年に渡って磨きぬかれた梁や柱に命を与えそこからまた長い歴史が育まれる。





高窓や天窓によって採り入れられた陽光が長年に渡って磨きぬかれた梁や柱に命を与えそこからまた長い歴史が育まれる。
Posted by 千鳥格子 at
10:08
│Comments(0)
2012年10月25日
左官鏝
これは私の祖父が使っていた左官鏝である。
つまみ面引き鏝といい土蔵などの窓の細かい面に使用される。
昭和の初めの頃のものだから一つ一つ手作りで作ったものだろう。
なんとも愛くるしいデザインである。
作為したモノより必要に応じて作られたモノの方がデザイン的にも優れている。


つまみ面引き鏝といい土蔵などの窓の細かい面に使用される。
昭和の初めの頃のものだから一つ一つ手作りで作ったものだろう。
なんとも愛くるしいデザインである。
作為したモノより必要に応じて作られたモノの方がデザイン的にも優れている。
Posted by 千鳥格子 at
16:50
│Comments(0)
2012年10月25日
2012年10月24日
2012年10月21日
台輪の金型
昭和8年から8年掛けて大改修された古川三之町上組の
屋臺(睛曜臺)の台輪部分の金型
昔の鍛冶仕事はすべて手ヤスリ掛けなので
質感が滑らかで極め細かいとのこと(小倉氏談)
大改修を手がけられたのは古川が誇る名工
上谷彦次郎氏

屋臺(睛曜臺)の台輪部分の金型
昔の鍛冶仕事はすべて手ヤスリ掛けなので
質感が滑らかで極め細かいとのこと(小倉氏談)
大改修を手がけられたのは古川が誇る名工
上谷彦次郎氏
Posted by 千鳥格子 at
09:30
│Comments(0)